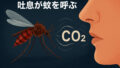2025年秋の新米シーズンを迎えましたが、全国的に新米の売れ行きが鈍いと報じられています。背景には、資材費や燃料費の高騰、輸入米の流通増加など、複数の要因が重なっています。福岡県筑紫野市で記者会見を行ったJA全農ふくれんの乗富幸雄・運営委員会会長は「コメが残らないよう、需要開拓の努力をしていかねばならない」と危機感を示しました。
お米の価格はなぜ上がっているのか?
店頭では5キロあたり5,000円前後という高値が目立ちます。これは昨年の約1.5倍以上。昨年の米不足を背景に仕入れ競争が過熱し、相場が一気に跳ね上がったことも要因とされています。
しかし消費者から見ると「なぜここまで高いのか?」と疑問を持つ方も多いはずです。実際には、肥料や燃料、農機具の価格上昇が直撃しています。例えば稲刈りに欠かせないコンバインは1台2,000万円前後。生産者にとっては非常に大きな投資であり、原価を理解してほしいという声が上がっています。
消費者の選択 ―「安い米」か「代替品」か
読売新聞オンラインで紹介されたアンケート(実施期間:2025年9月19日〜10月3日)は、まだ集計途中ではありますが、現時点での投票状況は以下の通りです(4,937人が回答)。
- 安い米を選んでいる:41.7%
- 米の購入を控えている:25.9%
- 特に変わらない:20.8%
- 代替品を選んでいる:10.4%
この数字からも分かるように、消費者の多くが価格を意識した買い方にシフトしている傾向が見えてきます。アンケートは終了後にさらに傾向が変わる可能性もあり、動向が注目されます。
専門家の見解
経済評論家は「5キロ4,500円を超える価格は適正水準とは言えない」と指摘。米価の高騰が続けば消費者の離反を招き、結果的に米余りによる価格暴落を招くリスクがあると警鐘を鳴らしています。
一方、農業経済の専門家は「報道のされ方にも問題がある」と指摘。農協ができるだけ小売価格を抑えてきた背景を説明しつつも、商系業者の動きによって価格が押し上げられている現状を強調しています。価格形成の仕組みを消費者が正しく理解することが重要だといえそうです。
私の体験
私自身も先日、地元農協のマーケットで4.5キロ3,750円のお米を購入しました。以前に比べれば高くなったと感じますが、食べてみるとやはり国産の新米ならではの甘みと香りがあり、美味しさに納得しました。
そうは言っても、消費者の本音
もちろん、生産者の努力やコスト増の現実を理解することは大切です。ただ、生活に直結するお米の価格については、消費者の立場からすると「安いに越したことはない」というのも正直な気持ちではないでしょうか。毎日食べる主食だからこそ、家計への影響は大きく、少しの値上がりでも負担感を覚える家庭が増えているのも現実です。
まとめ ― 米離れを防ぐには?
お米は日本の食文化の根幹であり、単なる価格競争では語り尽くせない価値があります。消費者にとっては「高い」と感じる一方で、生産者にとっては「ようやく適正に戻ってきた価格」という認識の違いがあります。
今後の課題は、消費者に原価や背景を知ってもらい、納得感を持って購入してもらうこと。さらに、外食や家庭での新しい食べ方提案など、需要拡大の工夫も求められます。
米価の高騰が続く今、私たち消費者は「安いから」「高いから」と単純に選ぶのではなく、その背後にある農業の現実にも目を向けることが大切ではないでしょうか。