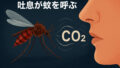近年、「ディズニー離れ」という言葉を耳にする機会が増えています。実際、東京ディズニーリゾートの入園者数はコロナ前の年間3000万人規模から、直近では2700万人前後にとどまっています。しかしその一方で、オリエンタルランドの業績は過去最高を更新し続けており、1人当たりの消費額は過去最高水準。つまり「客数は減っているのに、売上は伸びている」という不思議な状況が生まれています。
ディズニーの現状:数字と実態のギャップ 入園者数はコロナ前と比べてどう変わった?
ディズニーの入園者数がコロナ前より減っているのは事実ですが、これは必ずしも人気低下が原因ではありません。オリエンタルランドは「体験価値の向上」を目的に、あえて入場制限を設けています。コロナ禍に「空いていて快適なディズニー」を経験した人が多く、その心地よさを維持するために、戦略的に混雑を抑えているのです。
しかしこの施策は「入園者が戻っていない=人気が落ちた」と受け止められやすいジレンマを生んでいます。実際、顧客満足度調査では、USJや劇団四季に比べてディズニーの満足度は低下しているというデータもあり、数字上のギャップが「ディズニー離れ」の印象を強めています。
私自身もコロナ禍に訪れたとき、アトラクションが驚くほどスムーズに楽しめて「これが理想のディズニーだ」と感じた経験があります。その快適さを知ってしまった後では、通常時の混雑に戻った際に「前ほど楽しめない」と感じてしまうのも無理はないと思います。
でも実は、ゲスト1人あたりの売上高は過去最高を更新しており、2025年3月期の顧客単価は約1万7470円と高水準です。これは、価格の値上げやホテル事業の好調によるもの。つまり、「入園者数は少なくても、1人あたりの消費額を高める戦略」が成功しているのです。
値上げで変わる客層と不満の声
もう一つ大きな要因は、チケット価格の高騰です。現在では1万円を超える日もあり、気軽に訪れるのが難しくなりました。その結果、若年層の来園比率は減少し、40代以上の来園者が増加。実際に「昔のように気軽に行けなくなった」という声が増えています。
さらに、スマホを使った予約システムや有料サービスが導入され、「フラッと行って楽しむ」という従来のスタイルが難しくなったとの指摘も目立ちます。ショーの抽選、アトラクションの課金必須のシステム、朝イチでのチケット争奪戦…。こうした“スマホ依存型のパーク運営”にストレスを感じる人が少なくないのです。
正直、私も最近の「スマホ前提」のシステムには戸惑うことがあります。便利な反面、常に画面を見て次の予定を調整しなければならず、以前のように「その場での偶然や探検感」を楽しむ余裕が薄れた気がします。
SNS映えと関西シフトで強まる競合
近年、関西圏の観光需要が高まり、USJの存在感が一層強まっています。USJは映画・アニメ・ゲームなど多彩なコンテンツを抱えており、特に若い世代にとっては「SNS映えするスポットが多い」ことが魅力となっています。
一方でディズニーは、統一された世界観という強みがあるものの、「多様なコンテンツを一度に楽しみたい」という層にとっては物足りなく映る場合もあります。この点が、世代によってディズニー離れが進んでいると感じさせる要因のひとつでしょう。
USJのSNS映えを意識した仕掛けは非常に上手だと感じます。ディズニーももちろん魅力的ですが、若者が「映える体験」を求める時代においては、戦略を柔軟に変える必要があるのかもしれません。
それでもディズニーが「最強」であり続ける理由
短期的には、猛暑や値上げ、競合の台頭などで「勢いが落ちた」と言われるディズニーですが、長期的に見れば依然として圧倒的な存在感を誇ります。ファンタジースプリングスなどの新エリアやホテル事業は好調で、顧客単価は過去最高。さらに2035年に向けては、クルーズ船事業への参入という壮大な計画も進んでいます。
つまり「数は抑えつつ、質と単価で伸ばす」というビジネスモデルを確立しており、今後もしばらく日本のテーマパーク市場の中心であり続けることは間違いありません。
個人的には、ディズニーの「質を重視する姿勢」は評価したいです。入園者数の多さより、訪れた人がどれだけ充実した時間を過ごせるかに軸足を移した戦略は、長期的に見て正しい選択だと感じています。
ディズニーのキャラクターや世界観に対する熱狂的なファン層は、他のテーマパークにはない強みです。長期的なブランド価値とファンの支持を背景に、今後も安定した集客と収益を維持していくでしょう。
ネット上の主な声
- スマホ必須で気軽に楽しめなくなった
- 値上げが続き、家族連れには負担が大きい
- ショーの抽選や課金システムに疲れてしまう
- 「フラッと遊びに行ける場所」から「計画必須の高額レジャー」になってしまった
こうした声は、ディズニーが直面する課題を如実に表しています。今後は価格と利便性のバランス、そして誰もが楽しめる体験設計がますます重要になっていくでしょう。
まとめ
「ディズニー離れ」と言われる背景には、猛暑や価格高騰、スマホ依存のシステム、USJの台頭といった複数の要因があります。しかし実際の業績は過去最高水準であり、決して衰退しているわけではありません。むしろ、戦略的に入園者を抑えつつ、高付加価値ビジネスへと舵を切った結果なのです。
短期的には賛否が分かれる施策もありますが、長期的には日本のテーマパークのリーダーであり続けるでしょう。今後は、スマホ依存や価格面での課題をどう克服するのかに注目が集まりそうです。