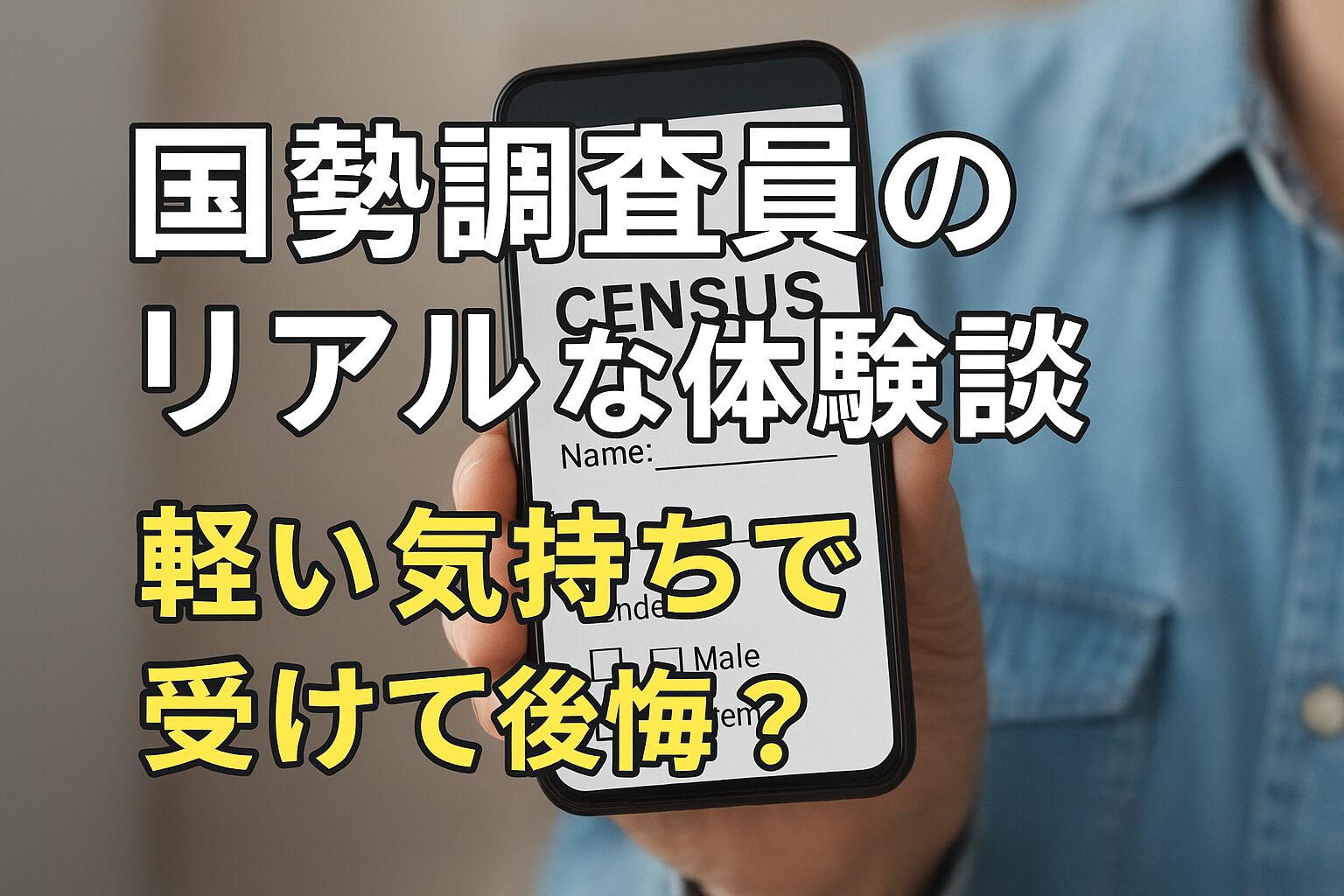5年に一度行われる国勢調査。実際に現場で活動する調査員の声を聞くと、その裏には想像以上の大変さと葛藤があることが分かります。今回は、広島市で調査員を務めた70代男性の体験談をもとに、国勢調査の課題と今後の改善点について考えてみます。
想像以上に大変な国勢調査員の仕事
国勢調査員は非常勤の国家公務員として報酬が支払われます。目安としては50世帯あたり5万円程度。年金暮らしの高齢者にとっては助かる収入源になりますが、仕事内容は決して楽ではありません。
- 担当区域は約80戸、一軒一軒の居住確認
- 配布資料の仕分けや封入作業
- 昼は留守家庭が多く、夜は警戒されるため訪問のタイミングが難しい
- 未回答世帯への繰り返しの訪問や聞き込み
顔写真付きの調査員証を下げていても、不審者扱いされる不安は常につきまといます。実際、詐欺被害が多い現代では仕方のないことかもしれませんが、心理的なストレスはかなり大きいようです。
調査員同士の支えと地域情報の共有
この男性の地域では、指導員が集会所を借りて作業場所を確保してくれました。そこで調査員同士が情報を交換し、例えば「この家は外国人世帯だから英語版が必要」「二世帯住宅だから2部必要」といった住民ならではの知識を共有できたそうです。
一人で抱え込んでいたら挫折していたかもしれないと話す男性。仲間の存在が精神的な支えになったことは間違いありません。
現場と制度のギャップ
国勢調査は原則「対面」での配布が推奨されています。しかし実際には、
- 昼間は不在家庭が多い
- 夜に訪ねると逆に警戒される
- ポスト投函せざるを得ないケースも多い
という現実があります。加えて「インターフォンを押さなかった」という苦情と「押されたら困る」という苦情が同時に寄せられるなど、板挟みになるケースも。制度と現場の間に大きなズレがあるのは明らかです。
ヤフコメから見える世論
この記事に寄せられた主な意見は以下のようなものでした。
- 調査員の負担や安全性、個人情報の扱いに課題がある
- 調査方法が前時代的であり、役所や民間業者に委託するべきではないか
- ポスト投函やオンライン回答を中心にすべき
多くの人が「現行の方法は時代に合っていない」と感じているのがよく分かります。
国勢調査はもっと効率化できるのでは?
国勢調査はもっと効率化できるのでは?
私自身、今回の国勢調査はスマホからインターネットで回答しました。操作もシンプルで、数分あれば終わってしまうのでとても便利でした。紙の配布や回収が本当に必要なのかと感じたのは、この手軽さを実感したからです。
実際、会社員であれば年末調整や確定申告の際に、住所・氏名・年齢・職業・勤務先・収入といった情報をすでに国に提出しています。こうした既存のデータを活用すれば、調査の大部分を代替できるのではないでしょうか。
もちろん統計上必要な情報は別にあるかもしれませんが、少なくとも「調査員が一軒一軒訪問する」という大規模な仕組みは、見直しの余地があると感じます。
まとめ:現場の声を反映した改善が必要
70代男性調査員の体験談から見えてきたのは、
- 調査員の高齢化と業務負担のギャップ
- 制度と現場の実情のズレ
- 個人情報管理や安全性への不安
という構造的な課題です。今後は、ポスト投函やオンライン回答を中心にする仕組みや、既存の行政データを活用する方法を検討すべきだと感じます。
国勢調査の目的は「国民の暮らしを把握して政策に活かすこと」です。その大切さは理解しつつも、調査員の負担と住民の不安を減らす改善が急務ではないでしょうか。