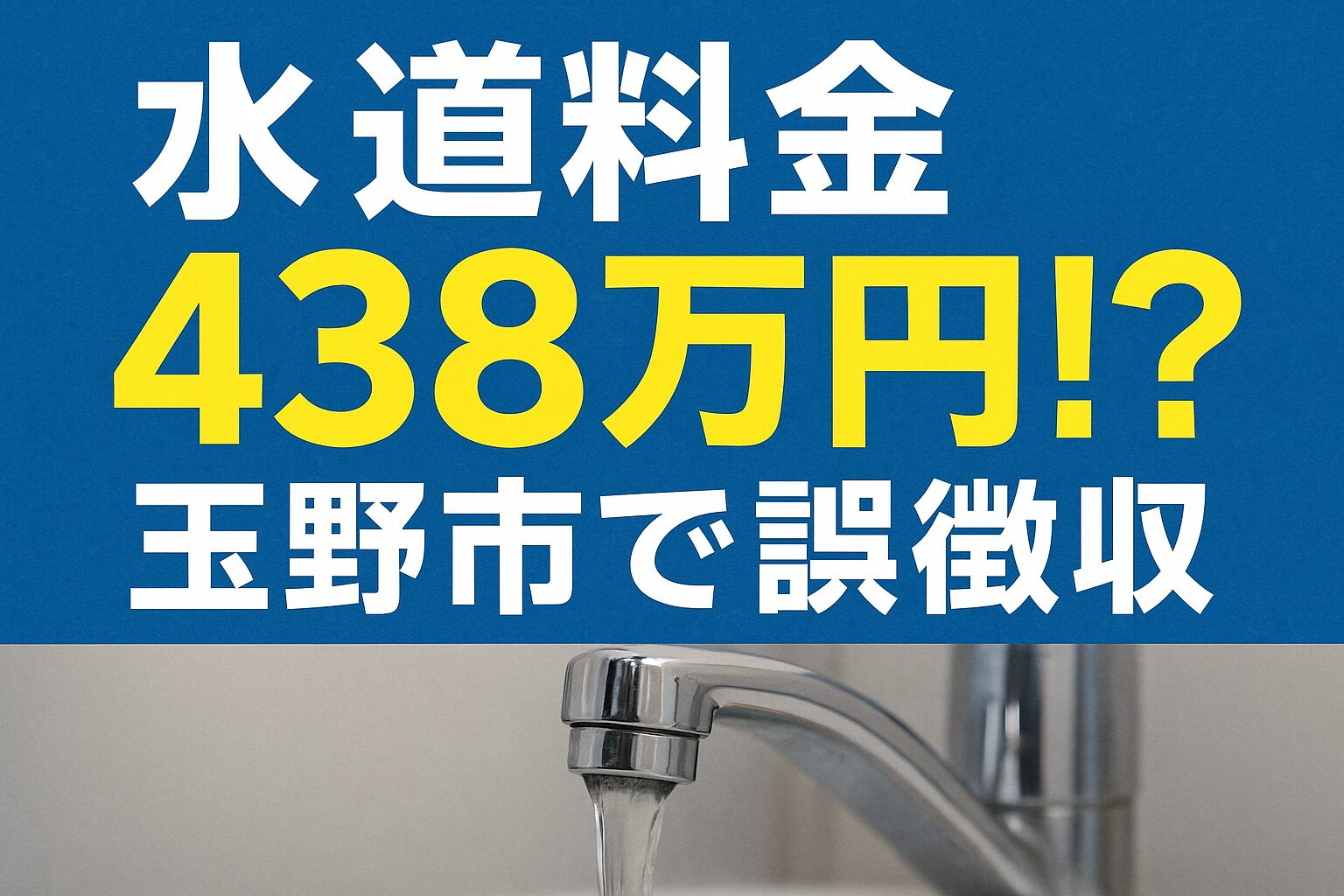岡山県玉野市で、1カ月の水道料金が本来1980円のはずが438万5436円として誤って徴収されるという前代未聞のトラブルが発生しました。市は入居者に謝罪し、全額返金と遅延損害金を支払いました。
誤徴収の原因は「入力ミス」と「確認漏れ」
玉野市の発表によると、6月に市職員が水道メーターを交換・開栓する際、本来は開始指針を「1」と入力すべきところ、誤って「245」と入力してしまったのが発端でした。その結果、実際には使用していない9756立方メートルもの使用量と計算され、あり得ない金額が請求されることになったのです。
さらに、契約している検針員によるチェック時にも異常値に気づかず、二重のミスが重なって徴収に至ったとのこと。発覚したのは、入居者が「口座から400万円以上引き落とされている」と問い合わせをしたことがきっかけでした。
市の対応と今後の再発防止策
玉野市は誤徴収分の返還とともに、利息相当の遅延損害金5764円も支払い、謝罪しました。再発防止策として「チェック体制の強化」や「事務手続きの見直し」を行うと発表しています。
ネット上の反応(ヤフコメ要約)
- 行政のシステムチェックが甘すぎる。AIや自動化システムを導入すべきでは?
- 公共料金の誤徴収は利用者が気づかないケースもあるため、金額に関わらず徹底確認が必要。
- 438万円を支払えたのかと驚いたが、自動引き落としだったのか。
- 開栓時の入力ミスに加えて、検針時にも気づかないのはあまりにも杜撰。民間企業のように異常値を検知するシステムを導入すべき。
まとめ
今回の玉野市の水道料金誤徴収は、入力ミスと確認不足が重なった結果生まれた大きなトラブルでした。公共料金は私たちの生活に直結するものだからこそ、自治体には二重三重のチェック体制が求められます。利用者としても通帳や引き落とし額を定期的に確認する習慣が必要かもしれません。
私自身、もしこのような誤徴収をされたらと考えると本当に恐ろしいです。普段は気づかないまま口座から自動引き落としされるケースが多いので、利用者側が気づけないリスクもあります。行政も「人のチェック」に頼りすぎず、システムによる異常検知を早急に導入した方が良いのではと思いました。